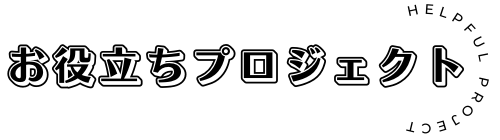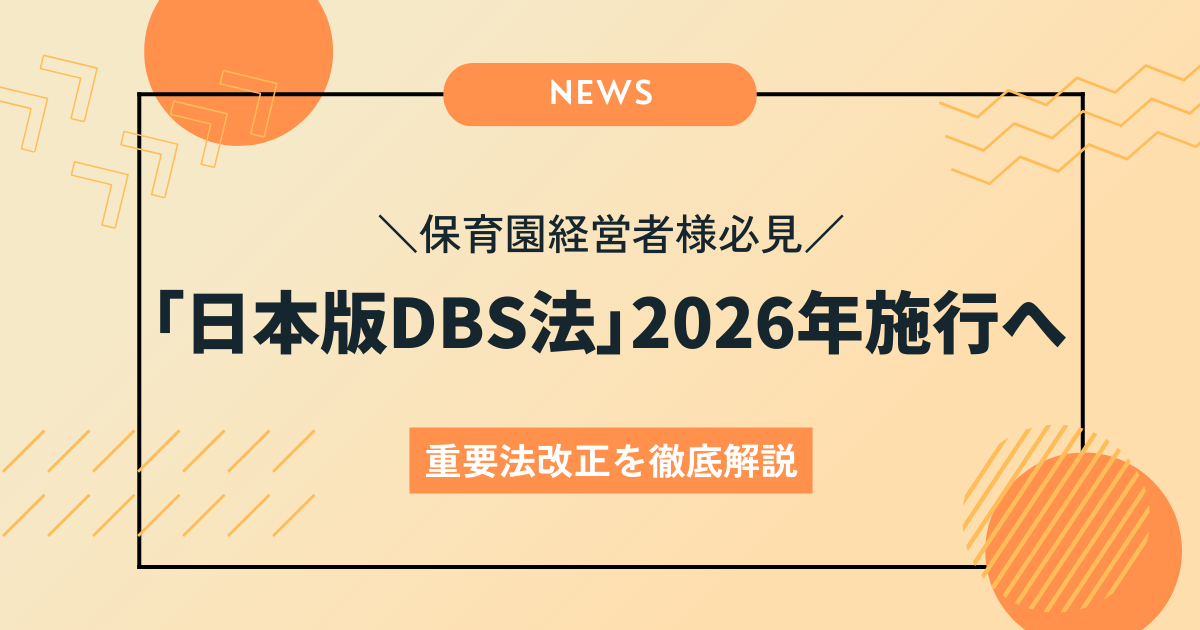2026年施行予定の「日本版DBS法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)。子どもたちの安全を守るためのこの新しい法律は、保育園の運営にこれまでにないレベルのコンプライアンス体制を求めます。
施行までまだ時間があるとお考えかもしれませんが、対応すべき項目は多岐にわたり、準備を怠れば法的なリスクはもちろん、将来的な保育園のブランディングや、事業承継・M&A(企業の合併・買収)の際に、企業の評価価値を大きく損なう致命的な要因ともなり得ます。
本記事では、保育園経営者の皆様が「知らなかった」では済まされない「日本版DBS法」の核心部分を、具体的な事例を交えながら徹底的に解説します。そして、これがなぜ保育園のブランディングやM&Aの成否を左右するのか、専門家の視点から明らかにしていきます。
「日本版DBS法」とは何か? なぜ保育園に必須なのか?
「日本版DBS法」とは、子どもと日常的に接する職業に就く人の性犯罪歴の有無を、事業者がこども家庭庁のシステムを通じて法務省に照会できる制度を定めた法律です。
立法の背景:社会からの強い要請
この法律が作られる直接のきっかけとなったのが、2020年頃に大きく報道されたベビーシッター仲介サイトでの事件です。この事件を機に、性犯罪歴のある人物が子どもと容易に接する機会を持ててしまう現状への社会的批判が高まり、政治主導で立法化が急速に進みました。つまり、この法律は子どもを性犯罪から守るという、社会全体の強い要請を背景に持っているのです。
保育園は「義務」の対象
この法律では、対象となる事業者が二種類に大別されます。
- 学校設置者等
法律や行政の認可・指定に基づき運営されている事業者。具体的には、学校、認定こども園、そして認可保育所や児童養護施設などが含まれます。 - 民間教育保育等事業者
上記以外の事業者で、学習塾やスイミングスクール、認可外保育所などが該当します。
重要なのは、後者の民間事業者が前科照会システムを利用するには、一定の基準を満たして内閣総理大臣の「認定」を受ける必要がありますが(任意加入)、認可保育所などが含まれる「学校設置者等」は、この法律で定められた措置を講じることが「義務」となる点です。つまり、認可保育所の経営者にとって、この法律への対応は選択肢ではなく、必須の経営課題となります。
保育園に課される具体的義務と実務フロー
では、具体的にどのような義務が課され、どのような手順で対応する必要があるのでしょうか。
義務①:職員の性犯罪歴の確認(前科照会)
これが本法の核となる義務です。
- 対象者
園長・保育士・保育補助など、子どもたちの保育や指導に直接従事する職員が対象です。ポイントは、子どもに対して「①支配性、②継続性、③閉鎖性」のある環境で接する人物かどうかです。例えば、直接保育は行わなくても、送迎バスの運転手が子どもたちの監督や指導を兼務している場合は対象となる可能性がありますが、単に運転業務のみを行う場合は対象外と考えられます。また雇用形態は問わず、業務委託の講師なども対象になり得ます。 - 照会タイミング
- 新規採用者: 採用後、実際に保育業務に従事させる前までに確認を完了させる必要があります。
- 既存職員: 法律施行後、3年以内に全対象職員の確認を終えなければなりません。
- 定期的確認: 一度確認すれば終わりではありません。5年に一度、定期的に確認を行う義務があります。なぜなら、こども家庭庁の資料によれば、性犯罪者のうち約半数は前科のない初犯者であるというデータがあり、採用時に問題がなくても、その後に犯罪を犯す可能性があるためです。
義務②:犯罪事実確認の具体的な流れ
前科照会は、保育園が直接法務省に問い合わせるわけではありません。以下のフローで行われます。
- 保育園→こども家庭庁
- 保育園が、対象職員(求職者も含む)の確認をこども家庭庁のシステムを通じて申請します。
- 職員→こども家庭庁
- 対象職員本人が、戸籍情報などの必要書類をこども家庭庁に提出します。
- こども家庭庁→法務大臣
- こども家庭庁が法務大臣に前科情報を照会します。
- 【重要】こども家庭庁→職員本人
- 性犯罪歴が「あり」と判明した場合、結果はまず職員(求職者)本人にのみ事前に通知されます。
- 職員(求職者)の選択
- 通知を受けた職員は、「内定を辞退する」「情報の訂正を請求する」といった選択ができます。本人が内定辞退を選んだ場合、その時点で手続きは終了し、保育園側は「性犯罪歴あり」という情報を知ることなく事態を収束できます。
- こども家庭庁→保育園
- 上記プロセスを経て、最終的な結果が「犯罪事実確認書」として保育園に届きます。
この仕組みは、事業者が不必要に機微な個人情報に触れるリスクを低減するための重要な設計です。また実際の制度施行前に変更がある可能性もありますので、ご注意ください。
経営者が知るべき「落とし穴」と具体的リスク事例
この法律への対応を誤ると、罰則や訴訟など、経営を揺るがす事態に発展しかねません。
リスク1:情報漏えいによる厳しい罰則
照会によって得られた「犯罪事実確認書」は、個人情報の中でも特に厳格な管理が求められます。
- 目的外利用・秘密漏示: 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- 不正な目的での提供: 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
ここで陥りがちな「落とし穴」が、善意による情報発信です。誤解しがちな**「アウトな事例」**を見てみましょう。
【アウトな事例1】
保護者へのアピールのため、SNSや園だよりで「当園の職員は全員、DBSの確認を行い犯罪歴がないことを確認済みです!安心してお子様をお預けください」と発信してしまった。
なぜアウトか?
「犯罪歴がない」という事実も、この法律で保護されるべき秘密情報です。これを外部に公表することは「秘密漏示」にあたります。
【アウトな事例2】
採用担当者が、不採用にした応募者について「不採用にした〇〇さん、確認書を見たら東京の△△に住んでたみたいだよ」と他の職員に話してしまった。
なぜアウトか?
犯罪事実確認書に記載された情報は、氏名、住所、生年月日などすべてが保護対象です。犯罪歴の有無だけでなく、付随する個人情報も漏らしてはなりません。
さらに、職員が離職した場合や応募者を不採用にした場合は、その日から30日以内に記録を完全に廃棄・消去する義務があり、これを怠ると50万円以下の罰金が科される可能性があります。
リスク2:労働法との複雑な関係性
性犯罪歴が確認された職員への対応は、非常にデリケートな問題を含みます。
- 採用内定者への対応
内定後に性犯罪歴が判明した場合、「内定取消し」を検討することになるでしょう。内定は法的には「解約権留保付労働契約」と解されており、その取り消しは解雇に準じて厳しく判断されます。ただし、性犯罪歴の存在は「採用内定当時に知ることができず、知ることが期待できない事実」にあたり、取り消しが認められる可能性は高いと考えられます。- 実務上の最適解
そもそも「DBS法の確認を通過すること」を採用内定の条件として明記し、確認が終わるまでは正式な内定を出さない、という運用が最もリスクを抑えられる方法です。
- 実務上の最適解
- 既存職員への対応
最も難しいのがこのケースです。法律は「児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるとき」に、「その者を教員等としてその本来の業務に従事させないことその他の必要な措置」を講じるよう義務付けています 。- 第一の選択肢は「配置転換」
まずは、子どもと一切接点のない事務職などへの配置転換が可能か検討しなければなりません。前述したように子どもたちの保育や指導に直接従事する職員が対象です。そこを避ければ雇用していることに法律上なんら問題は生じません。一番穏便に事を進められる選択肢であると言えるでしょう。 - 最終手段としての「解雇」
配置転換が不可能、あるいは本人が拒否した場合に解雇を検討しますが、これは労働契約法16条に基づき「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が厳格に問われます。採用時に経歴について質問していたか否かなど、様々な事情が考慮されるため、安易な解雇は無効と判断されるリスクが非常に高いです。
- 第一の選択肢は「配置転換」
これらの対応を誤り、漫然と雇用を継続した結果、万が一園内で事件が起きてしまった場合、園は安全配慮義務違反として極めて重い民事上の責任を問われることになります 。
日本版DBS法がM&Aの企業評価に与える致命的影響
保育業界では事業承継や規模拡大を目的としたM&Aが活発ですが、買い手企業はM&Aの最終契約前に「デューデリジェンス(DD)」と呼ばれる厳格な企業調査を行います。これは、売り手企業の法務、財務、労務などあらゆる側面を精査し、将来的なリスク(簿外債務)がないかを確認するプロセスです。
2026年以降、日本版DBS法へのコンプライアンス状況は、このデューデリジェンスにおける最重要チェック項目の一つとなり得ます。
買い手企業の弁護士やコンサルタントは、以下のような点を厳しくチェックするでしょう。
M&AにおけるDDチェックリスト例(DBS法関連)
- □ 日本版DBS法に対応した社内規程や情報管理マニュアルは整備されているか?
- □ 全職員(新規・既存)に対する犯罪事実確認を、法が定める期限内に適切に実施・記録しているか?
- □ 確認で得た機密情報の保管、アクセス制限、廃棄のプロセスは確立され、遵守されているか?
- □ 採用時の雇用契約書や内定通知書に、DBS法に関する適切な記載があるか?
- □ 過去に犯罪歴が判明した職員への対応(配転、解雇等)に関して、労働法上の紛争リスクを抱えていないか?
もし、これらの点で一つでも不備が見つかれば、それは買い手にとって予測不能な将来の負債を意味します。情報漏えいによる罰金や損害賠償、不当解雇による訴訟費用や解決金といった偶発債務のリスクは、M&Aにおける企業評価額(売却価格)から直接マイナス評価されるか、最悪の場合、リスクが大きすぎると判断されM&A交渉そのものが破談になる可能性も十分にあります。また、M&Aや事業承継を現状考えていない場合でも、さまざまなリスクに備えて準備を怠らないことが重要です。
まとめ:今こそ「守りの経営」で未来の企業価値を高める時
日本版DBS法は、刑事法、個人情報保護法、労働法という複数の法律分野が複雑に絡み合う、まさに「総合格闘技(Mixed Martial Arts)」のような法律です。その対応は、単なる事務作業ではなく、高度な法務・労務知識を要する経営マターそのものです。
施行は2026年12月25日が期限とされていますが、ガイドラインの策定などは2025年中に進められます。今から準備を始め、盤石なコンプライアンス体制を築くこと。それこそが、子どもたちの安全を守るという社会的責務を果たすと同時に、将来の事業承継やM&Aといった選択肢を確かなものにするための、最も賢明な経営判断と言えるでしょう。
このような法改正への対応を含め、自社の労務・法務体制を見直し、将来のM&Aに備えて企業価値を高めておく活動を**「プレM&A」**と呼びます。
弊社では、保育業界に特化した「プレM&Aコンサルティング」を提供しております。日本版DBS法への具体的な対応策の策定支援から、M&Aの際に買い手から高く評価される管理体制の構築まで、貴社の持続的な成長と企業価値の最大化をサポートいたします。
「何から手をつければ良いかわからない」「自社の体制に専門家の視点からのチェックを受けたい」とお考えの経営者様は、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。