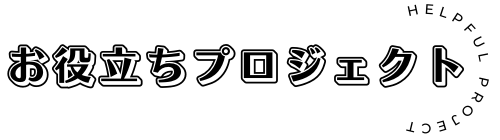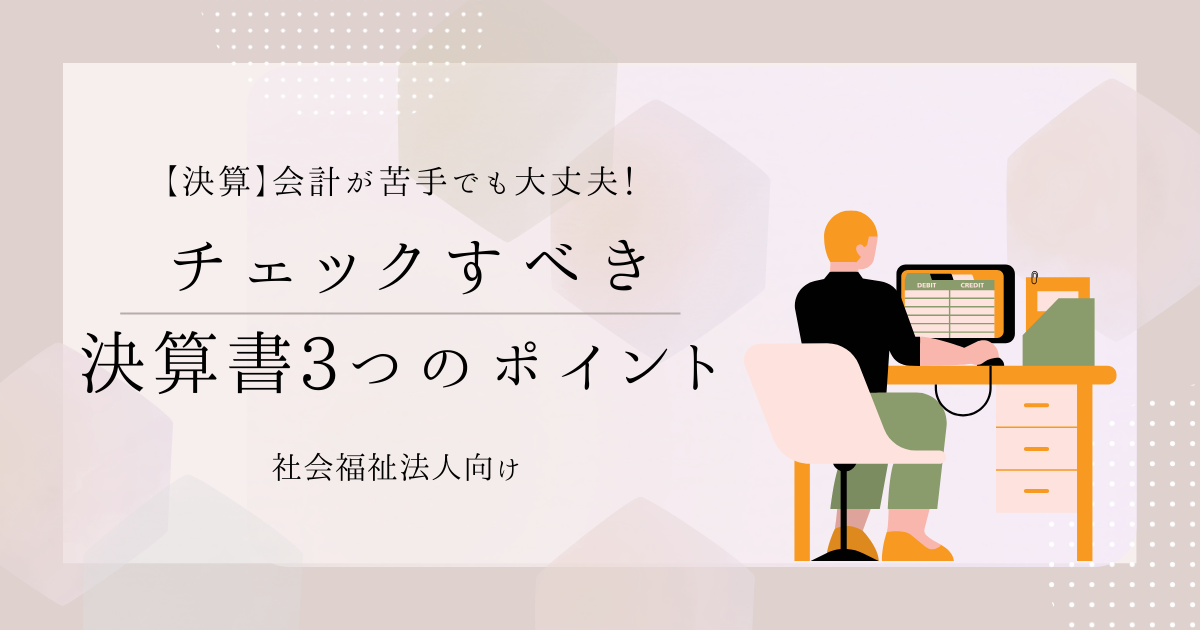「数字は苦手…」という理事長でも、毎年の決算書で“ここ”だけ押さえれば、法人の健康状態は一目でわかります。見るのは【貸借対照表】【事業活動計算書】【資金収支計算書】の3つ。この記事は専門用語を排し、**純資産は増えているか?借入に頼りすぎていないか?お金の流れはプラスか?**を短時間で判断できるようにまとめました。
会計数字を見るポイント!まず“ここだけ”理解をする
「数字は苦手…」でも大丈夫です。理事長が見るべきは3枚だけ。
貸借対照表(B/S)=体力、事業活動計算書(P/L)=実力、資金収支計算書(C/F)=呼吸。
この3枚を同じメガネで見れば、10分で「うちの健康状態」を把握できます。
- B/S:**純資産(貯金のようなもの)**は増えている?短期の支払いに困らない?
- P/L:本業で黒字?臨時の収入に頼っていない?
- C/F:お金の流れはプラス?返済で苦しくなっていない?(社福は支払資金という考え方で3区分表示します)
コツは「難しい言葉を聞き流し、見る場所を決め打ちする」ことです。
3つの計算書と「社会福祉法人vs株式会社」のちがい(全体像)
貸借対照表(B/S)=ある時点の持ち物と借金の一覧
- 何が載っている?
現金・預金、未収金、土地・建物などの資産。未払金・借入金などの負債。そして純資産(残り=体力)。前年数と並べて増減を見ます。
- 会社との違い
会社は株主の持分(資本金や剰余金)ですが、社会福祉法人は株主がいないので純資産として整理します(基本金、補助金関連の積立等もここなります)。
POINT
貸借対照表は今までの歴史が詰まったものです。それをある一時点で見た時の状態を表しています。そのため仮に今期が赤字でも、過去から積み上げてきたものがプラスであれば、当然純資産(体力)はプラスになりますし、ずっとマイナスであれば債務超過という形で表示されてしまいます。
事業活動計算書(P/L)=1年間の成果表
- 何が載っている?
純資産が1年でどれくらい増減したかを、収益と費用で示します。表示はサービス活動増減/サービス活動外増減/特別増減/繰越活動増減差額など
- 会社との違い
会社の損益計算書に似ていますが、補助金・寄附・臨時要因を明確に区分。本業(サービス活動)での力が見やすいのが社会福祉法人の特徴です。
POINT
事業活動計算書は今期の成績を表すものです。「今期はプラスだった」などの言葉で表現されるのはこの事業活動計算書の数字をみての状況です。基本的に1年単位で見ることが多く、過去からの積み上げ(創業時から今までの合計等)で数字を見るための物ではありません。
資金収支計算書(C/F)=お金の増減表
- 何が載っている?
1年の支払資金(≒すぐ支払いに使えるお金)の増減と内訳。事業活動/施設整備等/その他の3区分で表示します。
- 会社との違い
会社は「営業・投資・財務」の3区分。社福は支払資金という考え方を使い、予算運営(予備費・補正)とも相性がよい運用になっています。
POINT
資金収支計算書は今期の回収と使い道を表すものです。単純に期首と期末を見てお金が増えたか減ったかを視覚的に把握することもできます。経営において重要な資金のポジションを確認できる資料とも言えます。
B/S(貸借対照表)—「体力」を診る:ここだけ4点
結論:純資産が増え、短期資金に余裕があり、借入に過度に依存せず、未収・未払が滞っていなければ健全。
① 純資産の推移(前年→今年)
- 見る理由:組織の“貯金=体力”の積み上がり。右肩上がりなら将来の投資と突発対応に耐えやすい。
- 見方:B/Sの純資産欄を前年と比較して「↑/→/↓」を付ける。2年連続で減なら要対策。
② 流動比率=流動資産 ÷ 流動負債(目安100%)
- 見る理由:向こう1年の支払いに息切れしないかを見る指標。
- 見方:流動資産(現金・売掛・未収など)を流動負債(未払・短期借入など)で割る。100%未満は窮屈。
③ 借入金依存度=借入金 ÷ 総資産
- 見る理由:返済に追われる体質かをチェック。設備更新期は高めでもOKだが、**返済原資(後述のC/F)**が鍵。
- 見方:有利子負債の合計を総資産で割って割合を把握。
④ 未収・未払の滞留(事業未収金/事業未払金)
- 見る理由:お金が入らない/出しすぎは資金繰り悪化の芽。
- 見方:未収・未払の前期比と件数の古さを確認。決算では見越・繰延の整理も基本です。
ひとことで:体力=純資産。短距離(流動比率)も長距離(借入依存)も走れるか、足を引っ張る石(滞留)がないかを見る。ただし、借入金があることが必ずしも悪ではないという事に注意
P/L(事業活動計算書)—「実力」を診る:ここだけ3点
結論:最終の増減差額が黒字かだけでなく、本業(サービス活動)で黒字が出ているかを必ず分けて見る。
① 増減差額(ゴールの数値)と“中身”
- 見る理由:最終的に**増えた(黒)/減った(赤)**かがまず出発点。
- 見方:P/Lの最終行を確認 → 次に区分別(サービス活動/外/特別)で要因を分ける。
② サービス活動増減(本業の力)
- 見る理由:社福の“実力値”。公費・利用料などの収益構成と、人件費・給食費・減価償却等の費用構造を確認。
- 見方:前年と比べ、人件費比率の急上昇は要注意(配置・採用・残業の影響)。
③ サービス活動外/特別増減(イレギュラー)
- 見る理由:補助金・寄附・臨時要因に頼りすぎると、翌年に同じ成果は出にくい。
- 見方:補助・寄附は科目が明確(施設整備系・経常系など)。本業の黒字と切り分けて把握。
ひとことで:実力=本業が生んだ黒字。イレギュラーは“背伸び”なので、実力値からは一歩引いて見る。
C/F(資金収支計算書)—「呼吸」を診る:3色信号で直感チェック
結論:事業活動CFは緑(プラス)が基本。投資(施設整備等)は赤でも自然。借入・返済(その他)は無理がないかを見る。
① 事業活動による収支(緑:プラスが普通)
- 理由:日々の運営からお金が増える体質が必要。赤続きは構造課題。
- 根拠:資金収支は支払資金の増減を3区分で示します。
② 施設整備等による収支(赤:投資なら自然)
- 理由:建物や設備の更新は一時的にお金が出るのが普通。
- 見る観点:財源(補助・借入・内部留保)の手当てが計画どおりか。
③ その他の活動による収支(借入・返済)
- 理由:返済が重いと息切れします。
- 見る観点:返済の増減が事業活動CFを圧迫していないか。
予算×実績のズレは“即アラート”
社福は予算運営(予備費・補正)を前提にしています。ズレが出たら理事会で補正を検討。
ひとことで:呼吸=お金の流れ。平時は事業CFがプラス、投資は計画的、返済は背伸びしない。
「3枚をつなげて」読む(全体像のつかみ方・実践編)
1) なぜ“つなげて”読むのか?
単独の数値だけでは、体温だけ測って病名を当てるようなものです。
「P/L=実力」→「C/F=呼吸」→「B/S=体力」という原因と結果の流れで読むと、今期の出来事がお金と体力にどう効いたかが見えます。
- P/L(実力):今年、どの活動が増減の“原因”になったのか
- C/F(呼吸):その結果、実際のお金は増えたのか減ったのか
- B/S(体力):最終的に、貯金=純資産は増えたのか、弱ったのか
2) 良い循環(理想の型)
P/Lの本業黒字 → C/Fの事業活動プラス → B/Sの純資産増
この並びが連続して確認できれば、運営はうまく回っています。黒字が出ても未収が膨らんだり返済が重すぎると、お金は増えません。黒字=安全ではなく、「黒字が現金化されているか」まで見ることがポイントです。
3) 具体例(超シンプル・イメージ)
- P/L:サービス活動増減+500万円(=本業の黒字)
- C/F:事業活動+300万円(未収が200万円分ふえたため、黒字の一部しか現金化されていない)
- B/S:純資産+480万円(黒字分が主に積み上がる一方、設備修繕の前払で一部は資産に振替)
→ 対応:未収解消(請求・回収の運用強化)で、来期はP/Lの黒字→C/Fへより多く変換できる体制に。
4) 社会福祉法人と株式会社の“ゴールの違い”
- 株式会社:株主価値(株主への還元・時価総額)も重要な視点
- 社会福祉法人:公益の継続が最優先。だから「純資産の健全な積み上げ(余力)」と「事業活動キャッシュフローの安定(息切れしない運営)」を特に重視します。
※“見せかけの黒字”や“一時金頼み”では継続性が担保できません。
5) つなげ読み・実践プロトコル(会議用テンプレ)
- P/Lの区分別に「本業」「外部要因」「特別」を3色で要因整理
- C/Fで「事業活動」「施設整備等」「その他」を信号色(緑・赤・黄)で直感表示
- B/Sで「純資産」「流動比率」「未収・未払」の3点に丸×三角
- 最後に「P→C→Bの矢印」を紙面に手描き(何が何に効いたか一言で)
- “次の一手”を1つだけ決める(例:未収の90日以内解消/人件費配分の見直し/投資時期のスライド)
6) 要注意の“悪循環”サイン
- 本業は赤字なのに、補助・特別でたまたま黒字に見えている
- 黒字だが、未収や在庫が積み上がって事業活動C/Fが赤
- 借入返済でC/Fが圧迫 → 短期の支払い(流動比率)が常にギリギリ
このどれか1つでも当てはまるなら、構造対策(料金・稼働・配置・回収・返済スケジュール)が必要です。
運用計画に関してこちらも参照ください
用語ゼロからの超やさしい辞書(必要最小限・使いどころ付き)
純資産(じゅんしさん)
- 何か:資産から負債を引いた“残り”。法人の体力=余力。
- どう使う:前年と比べて増えているかを見る。減少が続くなら、運営か投資のどこかに無理がある合図。
流動資産/流動負債
- 何か:1年以内に現金化されるもの/支払うもの。
- どう使う:流動資産÷流動負債=流動比率で短距離走の余裕をチェック。100%未満なら、運転資金(支払いまでのつなぎ資金)に窮屈感。
減価償却(げんかしょうきゃく)
- 何か:建物や設備の“すり減り”を毎年の費用に配分するルール。現金の出入りは今はないが、P/Lには費用として出る。
- どう使う:黒字なのに現金が増えない理由の1つになり得る。C/Fで現金面を合わせて確認。
サービス活動(本業)
- 何か:社福の中核事業(保育・福祉サービスなど)。
- どう使う:P/Lのサービス活動増減が黒字かを最優先で見る。ここが赤なら、補助や臨時要因で黒字でも実力不足。
支払資金(しはらいしきん)
- 何か:すぐ支払いに使えるお金のイメージ。社福のC/Fは、この支払資金の増減を「事業活動」「施設整備等」「その他」で表す。
- どう使う:事業活動C/Fがプラスかをまず見る。投資(施設整備等)は赤でも自然、ただし財源手当(補助・借入・内部留保)をセットで確認。
理事長の「5分点検シート」(コピペして運用OK)
B/S(体力)
- 純資産(前年→今年):増/横ばい/減
- 流動比率:◯◯%(100%未満は注意)
- 借入依存度:◯◯%(返済原資とセットで)
- 未収・未払:滞留なし/あり(督促・締め見直し)
P/L(実力)
- 当期増減差額:黒/赤(区分別に要因把握)
- サービス活動増減:黒/赤(本業の実力)
- 補助・寄附依存度:◯◯%(平時から高依存は注意)
C/F(呼吸)
- 事業活動CF:+/−(ここが緑か)
- 施設整備CF:+/−(投資の裏づけ)
- その他CF:+/−(返済で窮屈になっていないか)
- 予算×実績の差:小/中/大 → 必要なら補正検討。
総合判定:良/注意/要対策
次アクション例:人件費配分の見直し/未収回収の強化/単価・稼働の改善/更新投資の時期調整/返済スケジュール再設計
よくある質問
-
黒字なのに現金が減っています。
-
利益と現金は一致しません。未収の増加・返済増・減価償却の影響などが要因。**資金収支(C/F)**で確認しましょう。
-
突発修繕で予算オーバーに。どうすべき?
-
社会福祉法人は予備費や補正予算の枠組みがあります。理事会で補正を検討し、計算書類・注記もルールに沿って対応します。
-
月次では何を追えば良い?
-
B/Sの流動比率、P/Lのサービス活動増減、C/Fの事業活動CFの3点だけを定点観測すると、年次のブレが小さくなります。
-
書類の保存は何年?
-
証憑など主要書類は原則10年保存が基本です。
まとめ(今日からできる“3ステップ”)
- 今日:このページをブックマークし、5分点検シートを理事長ファイルに差し込む。
- 今月:月次の3指標(流動比率/サービス活動増減/事業活動CF)を試算表から拾う仕組みを作る。
- 今期:投資や返済の計画をC/Fの3区分で理事会に共有。必要なら補正の選択肢を準備。