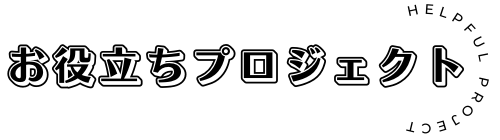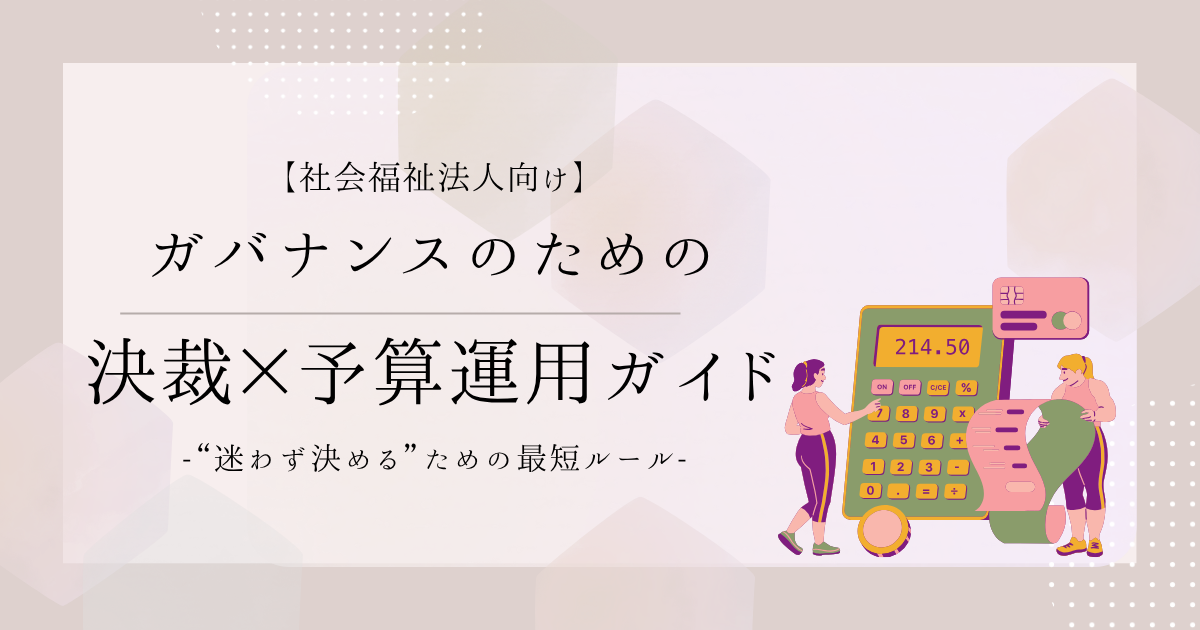問題提起:
保育の現場は毎日が本番。小さな備品購入から、大規模修繕、ICTの導入まで、意思決定のスピードが安全や品質を左右します。一方で、社会福祉法人は公益の継続が最優先。理事会・所轄庁・補助金の要件、監査や情報公開など、守るべきルールも多いのが現実です。
その結果、「誰がどこまで決めていいか不明確」「予算外対応が場当たり的」「稟議が重く、現場が止まる」という状態に陥りがち。これでは、スピードも透明性も両方失うことになります。
記事を読んでわかること:
- 決裁(やる/やらない)×決済(支払)×予算運用をひとつの軸に束ねる実務の型
- 社会福祉法人(保育園)に合わせたモデル権限表と、予算外・補正に効く**「審議パッケージ」(7点セット)**
- 月次・四半期・年次で“ブレを小さくする”運用ポイント
- 電子稟議・ワークフローにそのまま移植できる要件
- この記事を実装するためのDLテンプレ(決裁マトリクス、財源表、稟議フォーマット)
※難解な専門用語は最小限。**“今日から動かせる”**ことをゴールに書いています。
- 決裁マトリクス(予算内/予算外/予備費/流用)Excel
- 予算外・補正「審議パッケージ」稟議テンプレ(Word)
- 財源表&C/Fひな形(Excel)
はじめに:目的は「速くて安全な意思決定」
保育の質を安定して続けるには、日々の小さな支出から大きな投資まで、誰が・どこまで・どうやって決めるかが明確であることが大事です。
この記事では、数字や規程が得意でない理事長でもすぐ運用できるよう、決裁(やる/やらないの承認)と決済(支払い処理)、そして予算の考え方をひとつにまとめます。ポイントは「予算×権限」を一本化し、想定外の出費は予備費→流用→補正予算の順で落ち着いて処理することです。
覚えるべき基本用語
まずはそれぞれの用語を抑えていきましょう。
- 決裁:契約や発注の“可否”を上位者が承認する行為。
- 決済:請求書を確認し実際に支払う行為。
→ 同じ人が「起票→承認→支払い」まで一人で完結しない(けん制) - 予算:年度初めに理事会で決めた“使ってよい上限と内訳”。
- 予備費:小さな突発に備える枠。
- 流用:同じ部門内で科目間の付け替え。限度と承認者を決める。
- 補正予算:途中で前提が変わったときに、予算を組み替え直すこと。
社会福祉法人と一般企業の違い
一般企業は株主価値が重要となってきます。一方、社会福祉法人は公益の継続が最優先です。そのため意思決定では、
1)理事会の関与
2) 補助金・寄附の目的管理
3) 情報公開・監査
4) 資金繰りの安定(事業活動キャッシュフローが息切れしない範囲)
を特に重視します。
全体像を1枚でつかむ
まずはシンプルな図解を用いて基本を掴みましょう。
【図解】意思決定のながれ
P(予算) → 決裁(誰がどこまで) → 契約/発注 → 検収 → 決済(支払い)
↓(想定外が出たら)
予備費 → 流用 → 補正予算(理事会で組み替え)
つまり、予算は土台となるものです。予算の範囲なら決裁ラインに従って速く進め、想定外は“正面から”手続きを踏んで安全に処理します。
社会福祉法人の保育園を想定したモデル権限
では次に、社会福祉法人の保育園を想定とした決裁権限等のモデルを見ていきます。各法人、施設の規模感に併せてここをベースにカスタマイズしてください。
役割例:理事会/理事長/事務局長(本部長)/園長/主任/会計担当
契約・発注(物品・業務委託など)
〜30万円:園長(主任が起票/相見積1社以上)
30〜100万円:事務局長(見積比較・仕様書)
100〜300万円:理事長(総務・会計のレビュー付き)
300〜1,000万円:理事会(反社・法務レビュー、財源表を添付)
1,000万円超:理事会+必要に応じ評議員会
※リースやサブスクは契約総額で判定。分割は合算で判定。
設備投資・施設整備
〜100万円:事務局長(園長提案)
100〜500万円:理事長(相見積2社以上、工事監理計画)
500万円超:理事会(補助/借入/内部留保の財源構成+C/F影響を必須添付)
購買(備品・消耗品・IT)
〜10万円:園長(主任起票)
10〜50万円:事務局長(セキュリティ・資産台帳登録)
50万円超:理事長
人事(採用・等級)
一般~主任:園長提案→事務局長承認
園長・本部管理職:理事長承認
レンジ外・特例:理事会
寄附・助成
受入:事務局長→理事長(使途制限の目的コード登録)
拠出:〜30万円理事長/30万円超理事会
借入・資産処分
借入/長期リース:理事会(返済計画・資金繰り)
資産取得/処分:理事会(所轄庁協議が必要な場合あり)
年商・園数・契約金額帯を反映した“即使える版”をお渡しします。
「予算×権限」をつなぐ運用ルール(迷ったらここを見る)
1) 予算内
当初予算の科目・金額・目的の範囲内なら、上記の「モデル権限」に従って進めてOK。
2) 予算外(想定外)
〜50万円:事務局長(72時間以内に理事長へ事後報告)
50〜200万円:理事長(次回理事会で報告)
200万円超:理事会で補正予算(後述の審議パッケージを必ず添付)
※緊急修繕などは「仮承認→即時発注→稟議→報告」で安全に。
3) 予備費の取り崩し(小さな突発)
〜30万円:園長→事務局長承認(用途・根拠を台帳記録)
30〜100万円:理事長承認(残高・累計をダッシュボード共有)
100万円超:理事会(実質補正扱い)
※用途は安全衛生・制度対応・緊急修繕などに限定。
4) 流用(同じ部門内で科目の付け替え)
10%以内:事務局長
10〜20%:理事長
20%超:理事会(実質補正)
※補助・寄附など使途制限のあるお金は流用不可。
5) 繰越(翌期へ持ち越し)
100万円未満:理事長
100万円以上:理事会+所轄庁協議(必要に応じて)
※契約・工期などの明確な理由が前提。
予算外・補正の「審議パッケージ」(7点セット)
予算外の支出や補正予算は、理事長や理事会にとって判断の難所です。ここを早く、そして安全に通過させるために、稟議書に「7つの論点」を一枚にまとめる。これだけで審議時間は半分以下になり、監査対応もスムーズになります。以下、それぞれを文章としてどう書くか、例文付きで解説します。
1. 前提変化の事実(何が起きたのか/なぜ今か)
まず「何が起きたのか」を、主観を入れずに短く書きます。原因・事実・緊急度の順で、最大5行を目安に。
例文:
6月15日、〇〇園のボイラーが故障。業者診断により、熱交換器の破損で修理不可、交換が唯一の選択肢と判明(診断書添付)。
安全衛生上、今期中の復旧が不可欠。仮設機のリースはランニングが高額で非効率(比較表添付)。
良い書き方のポイント:
“形容詞”ではなく“名詞+日付+根拠”。
「誰の診断か」「文書は何か」を添付資料名で示す。
2. 財源表(補助/借入/内部留保の組み合わせ)
“どうやって払うか”を一目でわかる形に。支出総額に対して、(1)補助金、(2)借入、(3)内部留保の3つの積み木で財源を組みます。文章では以下の順で明記します。
例文:
総事業費:1,800万円
財源内訳:
(1) 設備補助金見込 900万円(採択待ち:結果8月)
(2) 借入 600万円(金利1.1%、5年返済、試算表添付)
(3) 内部留保 300万円(前期末の施設整備積立から充当)
ポイント:
“確度”を色分け(確定=緑/見込=黄/未定=灰)など、文章に簡単な注記を付ける。
補助金がダメだった場合の代替財源(例:借入上積み、規模縮小)も一行で。
3. C/F(資金収支)への影響(息切れしないか)
「投資しても息切れしないか」を、事業活動/施設整備等/その他の3区分で“ことば”にします。難しい数式より、“今と来期の呼吸”を示すのがコツ。
例文:
事業活動CF:現状プラス(▲には転じない見込み)。運転費の増減は軽微。
施設整備CF:本件実行で当期はマイナス(自然な投資)。翌期以降は平常化。
その他CF:借入実行により当期はプラス、翌期以降は返済により年▲120万円のマイナス。
結論:当期・翌期ともに資金ショートの見込みなし(月次資金繰り表添付)。
ポイント:
“専門用語なし”で今期と来期を1行ずつ。
返済額は年額で提示し、事業活動CFで吸収できるかを言い切る。
4. 代替案の比較(やり方の選択肢)
A:全交換(本提案)/B:仮設+延命/C:時期延期 など、最低2案は並べます。文章は「コスト+品質+安全」の3切り口で。
例文(要約):
A案:全交換(1,800万円)…初期コスト高だが故障リスク解消、効率改善でランニング低下。安全性高。
B案:仮設+延命(800万円)…初期安いが、1年以内に再投資の可能性高。ランニング高、二重コスト。
C案:延期(0円)…安全性に問題、保育提供に支障。不可。
結論:A案が最適(総コストと安全衛生の観点)。
5. 優先順位の入れ替え(何を後ろ倒しするか)
補正は“風呂敷を広げる”行為にならないよう、代わりに何を遅らせるかを必ず書きます。
例文:
予定していた遊具更新(500万円)は翌期へ繰越、見積は維持。
ICT端末の追加配備(200万円)は数量を半減、学期末に再審議。
これで、読んだ人は「財源だけでなく、全体の優先順位を再設計した」と理解できます。
6. リスク(やらない場合の影響)
理事会が最も気にするのは“何が起こるか”。安全、品質、法令、対外評価の順で、事実ベースに。
例文:
安全:温水供給停止が長期化すると衛生リスク。臨時休園の可能性。
品質:給食提供や入浴に恒常的な影響。保護者満足度の低下。
法令:所管の指導・監査で是正指示の可能性。
対外:ウェイティングリストの減少=収益性への影響。
7. 合議(誰と擦り合わせたか)
「現場・本部・経理・必要に応じて専門職」と顔ぶれを明示します。ここが曖昧だと、理事会は不安になります。
例文:
園長(現場ニーズ・安全衛生)/事務局長(契約・調達)/会計担当(資金繰り)/設備業者(技術)。
事前合議済み。利害関係者の取引なし(確認書添付)。
- 前提変化の事実(例文入り)
- 財源表(補助/借入/内部留保の積み木)
- C/F影響(今期と来期の“呼吸”)
- 代替案比較(コスト・安全・品質)
- 優先順位の入替(後ろ倒しの明記)
- リスク(やらない場合)
- 合議の顔ぶれ(責任の所在)
【図解】予算外に出た時の“落ち着いた流れ”
事実確認 → 小口なら予備費 → 同一部門内で流用検討 → 足りなければ補正予算 → 理事会審議(7点セット)
月次・四半期・年次の「最低限運用」
ここまで、一連の流れとして予算運用の考え方を説明しましたが、年間のスケジュールベースで考えた時に、月次・四半期・年次でどの程度抑えるべきかを改めてみていきたいと思います。
月次(P−A−Fとアラート)
月次ではなるべくタイムリーにかつ分かりやすく情報を共有する事が重要視されています。そのため、「予算(P)に対して実績(A)は+2%」「見込み(F)は期末で▲3%」のように、同じ表現で毎月報告をするよう心掛けると、分かりやすく関係者に伝わるようになります。またP(予算)−A(実績)−F(見込み)で乖離を色分け(±5%=緑、±5~10%=黄、±10%超=赤 など)し、赤は対策文を必ず1行添付などの工夫も重要です。
四半期(棚卸し)
四半期は一つの会計期間として、単月(月次)のタイムリー差み併せて、精度の高い情報も求めるようになります。そのため契約の更新予定(自動更新含む)や価格改定の予定を一覧化し、「放置の高止まり」を防ぎ、月次レベルでは実施できない点にも足を踏み入れるとよいでしょう。また投資案件は「見積・補助・借入・スケジュール」の4点セットで進捗を確認し、予備費残にも目を配りましょう。
年次(構造見直し)
年次は1年間の総まとめになります。また、今後の予算の指標にもなり得る情報ですので、「今年の予算外は〇〇件、金額△△万円。そのうち安全衛生が□□%」のように定量化して財務(会計)外のデータと併せた情報の整理が重要です。この数値を来期の予備費設定や基準金額の見直しに直結させる、P/L→C/F→B/S(本業→現金→体力)の循環の総点検を行いましょう。
月次~年次に関わらず見たいポイント
【図解】P→C→Bの“良い循環”
P/L(本業の黒字)→ C/F(事業活動プラス)→ B/S(純資産増)
※黒字でも未収が膨らめば現金は増えません。「黒字=安全」ではなく、黒字が現金化されているかまで見るのがコツ。
電子稟議・ワークフロー導入のコツ
ここまで、決裁権限と予算管理についてみてきましたが、これらを進めるにあたっては稟議が必要不可欠です。しかし、統制の取れた環境を整えるにはこれらの稟議をしっかり管理しなければならず、業務の煩雑性が増して、業務負荷が増大する恐れがあります。
このような問題を解決するため、こういった業務を便利にするICTツール、電子稟議やワークフローの活用法と導入のポイントをご紹介します。
- 先に紙で(業務×金額)×役割のマトリクスを完成。
これが承認ルートなどのベースになる物で、一番重要なポイントです。 - それをそのままシステムの承認経路に移植できるシステムか確認
必須項目をシステムで強制入力できるか確認。
(前提変化/財源表/C/F/代替案/優先順位/リスク/合議など) - 合議(並列)承認に対応できるか確認
園長と本部の両承認が必須など、実務に沿った動きができるかが重要です。 - 添付の種類を固定したり、ダッシュボードで自動集計できるものか確認
診断書、見積比較、資金繰り表、借入条件、補助要綱、反社チェックを添付出来たり、予備費残高/流用履歴/予算外件数をクエリレポートで確認できるか - 監査用にCSV/PDFエクスポートが簡単か。
監査の際に業務が楽になります。 - モバイル承認可
必須ではないですが、現場でのスピード感が上がります。
このような点は確認すると良いでしょう。
まとめ:速くて安全な意思決定は「予算×権限×手続」の一本化から
- 予算が土台。範囲内はモデル権限で迷わず進め、想定外は予備費→流用→補正の順で“正面から”処理。
- **審議パッケージ(7点セット)**をテンプレ化すれば、理事会の判断は速く、監査も強い。
- **P→C→Bの循環(本業→現金→体力)**を月次・四半期・年次の同じ言い回しで点検し、ズレは色分け+一行対策。
- 電子稟議は**(業務×金額)×役割のマトリクス**をそのまま承認経路へ。並列承認・必須項目・添付の型が入れば運用は安定。
次の一歩
- 記事内のモデル権限を自法人規模に合わせて初期設定
- 「審議パッケージ」テンプレを配布して全園・本部で書式統一
- 電子稟議への移植要件(並列承認・CSV/PDF出力など)をツールに照合
- 決裁マトリクスの金額しきい値を年商・園数に最適化
- 予算外・補正の「審議パッケージ」を貴法人の書式へ移植
- 電子稟議の承認経路(並列・必須項目・添付型)を設計