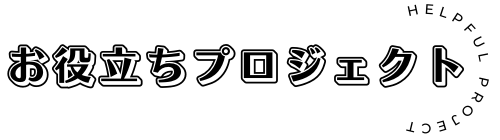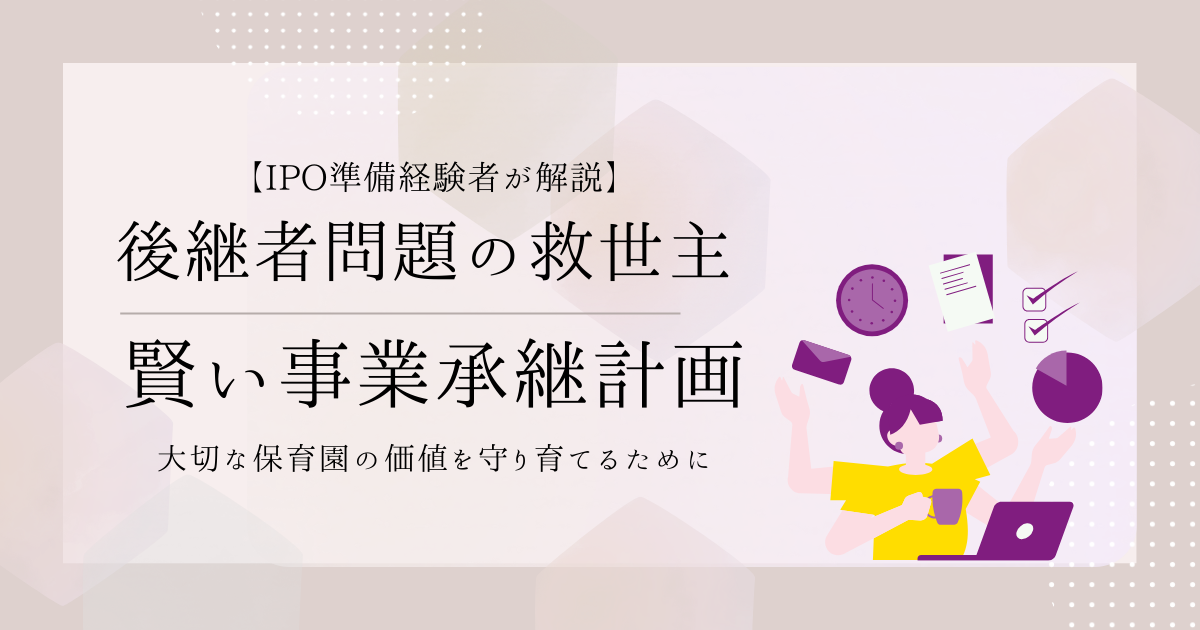はじめに:保育園経営の悩みは、決してあなた一人だけではありません
「自分が動けなくなったら、この園はどうなってしまうのだろう…」 「長年愛情を注いできたこの場所を、私の代で終わりにしたくない…」
保育園の経営者であるあなたが、もし今、後継者がいないことで、夜も眠れないほどの不安を抱えていらっしゃるなら、まずお伝えしたいことがあります。そのお悩みは、決してあなた一人だけのものではありません。
私はかつて、上場を目指す企業の経営企画室で、事業の根幹を支える仕事に携わってきました。そして独立後、多くの経営者の方々と向き合う中で、特に保育園という、未来そのものを育む尊い事業において、多くの園長先生が「事業承継」という非常に重く、しかし避けては通れない課題に直面している現実を目の当たりにしてきました。
長年かけて築き上げてきた、子どもたちの笑顔と成長に満ちたこの場所。信頼してくださる保護者の皆様と、共に汗を流してきた職員たち。その全てを、誰に、どうやって託していくのか。
この記事では、そんなあなたの深いお悩みに寄り添い、不安を希望に変えるための「賢い事業承継計画」について、経営のプロフェッショナルとしての視点から、分かりやすく解説していきます。これは「終わり」を考えるための話ではありません。あなたが大切に育んできた価値を、未来永劫へと繋いでいくための「始まり」の物語です。
忍び寄る「閉園の波」:データが示す保育園経営の厳しい現実
「長年、地域の子育てを支えてきたこの園だけは大丈夫」—。 そう願うお気持ちとは裏腹に、今、これまで「安定」の代名詞であった保育園経営そのものが、静かに、しかし急速に、その基盤を揺るがされています。
株式会社帝国データバンクの「『保育園』の倒産・休廃業解散動向(2025年上半期)」によると、2025年1月~6月の保育園事業者の倒産・休廃業・解散は22件で、前年同期の13件から約7割も増加しました。これは、過去最悪のペースだった前年同期をさらに上回る水準であり、このまま推移すれば年間での過去最多記録を大幅に更新することは、もはや確実な情勢です。しかし、これは氷山の一角に過ぎません。倒産という形で表面化せずとも、経営者の高齢や心労などを理由に、自主的に事業をたたむ「休廃業・解散」は、統計上の数字の何倍にも上ると言われています。
その背景には、もはや個々の努力だけでは乗り越えがたい、複合的な要因が存在します。 長引く物価高騰は、給食材料費や光熱費を容赦なく圧迫し、深刻な保育士不足は人件費の高騰を招いています。一方で、地域によっては少子化の影響が顕在化し、定員割れによる収入の減少に苦しむ園も少なくありません。
「子どものための事業だから、利益は二の次」という美しい理念だけでは、職員の生活も、園の未来も守れない。もはや立ち行かない時代に突入しているのです。そして、こうした厳しい経営環境の中で、事業継続の最後の砦となるべき**「次の担い手」がいない**という問題が、多くの保育園に重くのしかかっています。
では、なぜ、これほどまでに後継者を見つけることが難しくなってしまったのでしょうか。その背景には、個人の努力だけではどうにもならない、いくつかの構造的な要因が存在するのです。
なぜ今、保育園の「後継者不足」が深刻化しているのか?
「昔は、子どもが後を継ぐのが当たり前だったのに…」そう思われるかもしれません。しかし、時代は大きく変わり、保育園における後継者不足は、個人の問題ではなく、社会構造の変化に根差した深刻な課題となっています。
親族内承継のハードル:変化する家族のカタチと価値観
かつて事業承継の主役だった「我が子へ」という選択肢は、今や当たり前ではなくなりました。少子化はもちろんのこと、子どもたちが自身のキャリアや人生を自由に選択する時代となり、必ずしも親の事業を継ぐことを望まないケースが増えています。また、保育園経営は、早朝から夜遅くまで、365日気の休まる時がないほどの激務です。その大変さを誰よりも知っているからこそ、「自分の子どもに同じ苦労をさせたくない」と考える経営者の方も少なくありません。
職員への承継の困難さ:保育士不足と経営能力の壁
「信頼できる職員に継いでもらえれば…」と考えるのは自然なことです。しかし、これもまた簡単ではありません。まず、慢性的な保育士不足の中、園長という重責を担ってくれる人材を見つけること自体が困難です。さらに、優秀な保育士が、必ずしも優秀な「経営者」であるとは限りません。保育の知識と、資金繰りや労務管理、行政対応といった経営スキルは全くの別物です。加えて、個人が保育園を買い取るための資金(株式取得費用や借入金の個人保証など)を準備するのも、極めて高いハードルとなります。
このまま放置した場合の静かなリスク
後継者問題は、「まだ自分は元気だから」と先送りにされがちな問題です。しかし、もし経営者であるあなたに万が一のことがあった場合、準備がなければ園は立ち行かなくなり、最悪の場合、突然の閉園という事態に陥りかねません。それは、通い慣れた園を失う子どもたち、職を失う職員たち、そして預け先に窮する保護者の方々と、関わる全ての人を不幸にしてしまいます。問題の深刻さは、まさに「待ったなし」の状況なのです。
未来を繋ぐ3つの選択肢とは?
では、打つ手はないのでしょうか?いいえ、そんなことはありません。あなたの園の未来を繋ぐための選択肢は、確実に存在します。大切なのは、視野を広く持ち、早期に検討を始めることです。
選択肢①:親族・職員への承継(時間をかけた育成プラン)
もし候補者がいるのであれば、これが最も理想的な形の一つです。しかし、実現には最低でも5年以上の準備期間が必要です。単に「後を頼む」だけでなく、かの渋沢栄一も提唱した王道経営学(財務、労務、法務などの知識はもちろんのこと、企業は「社会の困りごとを解決する」という本来の存在意義を持ち、長期的な社会全体の繁栄を目指すべきだという考え方)を伝え、金融機関との関係を構築し、計画的に株式を譲渡していく、という緻密な計画が不可欠です。
選択肢②:第三者への譲渡(M&Aによるハッピーリタイアメント)
近年、最も現実的で有力な選択肢として注目されているのが、M&Aです。これを聞いて「身売り」「乗っ取り」といったネガティブなイメージを抱く方がいらっしゃるかもしれませんが、現代の保育園M&Aは全く違います。あなたの保育理念や想いを理解し、引き継いでくれる、より経営基盤の安定した企業や社会福祉法人に園を託す、前向きな経営戦略なのです。これにより、あなたは創業者利益を確保して安心して引退でき、職員の雇用は守られ、子どもたちはより充実した環境で育っていく、という「三方よし」の未来が実現可能です。
選択肢③:段階的な経営委任(緩やかな引退プラン)
すぐに経営から完全に手を引くのではなく、外部から新しい経営者や園長を招聘し、あなた自身は理事長や場合によっては顧問として数年間、経営をサポートするという形です。新しい体制への移行をじっくり見届けながら、緩やかに引退していくことができます。
M&Aを考える前に。今、あなたの園の「本当の価値」を知る準備
どの選択肢を選ぶにせよ、まず始めなければならないのは、**「あなたの園の現状を正しく知る」**ことです。M&Aを検討する上でも、この準備が成功の鍵を握ります。
「自園の価値」を客観的に把握する
不安の正体は、分からないことにあります。まずは、あなたの園の「健康診断」をしましょう。財務諸表を整理し、資産や負債、収益の状況を正確に把握します。同時に、数字には表れない「強み」もリストアップします。「地域での評判が良い」「食育に力を入れている」「離職率が低い」…これらはあくまでほんの一例に過ぎません。ご自身では些細なことと思っていることですら、あなたの園の素晴らしい価値になり得るです。
あなたの「想い」を言葉にする
あなたは、どんな想いでこの園を立ち上げ(或いは先代から引き継いで)、運営してきましたか?これから先の園に、何を一番大切にしてほしいですか?「子どもたちの主体性を尊重する」「職員が安心して長く働ける環境」…この「想い」こそが、M&Aにおいて最も重要な引き継ぎ事項です。最適なパートナーを見つけるための、道しるべとなります。
一人で悩まず、専門家に相談する
事業承継は、経営者人生における最大級のプロジェクトです。税務、法務、財務、そして何より業界への深い知見が求められます。一人で、あるいはご家族だけで抱え込むのには限界があります。早い段階で、保育業界の事情を深く理解した信頼できる専門家に相談すること。それが、後悔のない、最良の選択をするための最も確実な近道です。
まとめ:大切なのは「子どもたちの未来」を第一に考える決断
後継者がいないという現実は、決してあなたの経営者人生の失敗ではありません。むしろ、時代の変化の中で、園と子どもたちの未来を真剣に考え、次の最適な形を模索する、という新たな経営判断を求められている証拠です.
事業承継の準備は、あなたの引退のためだけに行うものではありません。それは、あなたが愛情を注いできた園に通う子どもたち、日々の保育を支える職員たち、そして信頼を寄せてくれる保護者と地域社会、その全ての未来を守るための、経営者としての最後で最大の責務です。
あなたの築き上げてきた素晴らしい価値と、未来へ託したい大切な想い。その二つを両立させる道は、必ずあります。
もし、少しでも心の中のもやもやが晴れない、何から手をつけていいか分からない、という状況でしたら、ぜひ一度、お話をお聞かせください。私は、あなたの園の価値を正しく評価し、あなたの想いを最大限に尊重しながら、共に未来を考えるパートナーです。まずは無料の個別相談で、あなたのその深いお悩みをお聞かせいただけませんか。