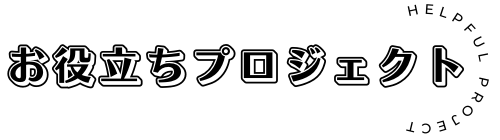問題提起:子どもの成長には欠かせない重要な役割を果たしているのが食事です。保育園では毎日当たり前のように給食が提供されていますが、1日の多くの時間を保育園で過ごす子どもにとって給食はとても重要であり、楽しみの1つでもあります。給食作成や提供は実際どのように行われているのでしょうか?そもそもどうして給食が必要なのでしょうか?
この記事を読んでわかること:この記事では給食の特徴や役割ついて詳しく説明しています。また、給食の作成・提供方法には違いがあり、園に合わせた環境をどのように整えるかが重要です。幼稚園との制度の違いも説明しており、保育園給食の全体像を体系的かつ実践的に理解することができます。
保育園給食の特徴とは
保育園給食は、単なる食事提供だけではなく、子どもたちの食文化の理解や健康的な食習慣の形成にもつながる貴重な機会です。認可保育園は給食を提供することが義務付けられており、調理室の設置も必要です。厚生労働省がガイドラインを設けており、その基準を満たした給食の提供をすることが必須となっています。
給食が提供されるメリットと課題
保育園で給食が提供されることは子どもの成長や教育、保護者の負担軽減など、多くのメリットを持っています。
軽視できない!保育園の給食提供でもたらされるメリット
子どもの栄養バランスを確保
保育園給食は厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」を参考に、子どもが必要な栄養素を適切に摂取できるよう献立が作られます。保育園で食べる給食とおやつで幼児(3~5歳児)は1日の45%を、乳児(1~2歳児)は50%を満たすように献立が作成されます。おやつには食事で足りない栄養素を補う補食のような役割があります。
年齢に応じた食事内容・アレルギー対応
乳児と幼児では食べる量や食材の形状が異なるため、発達段階に応じた食事が提供されます。離乳食対応も行われます。 また、食物アレルギーを持つ子どもには、個別対応の食事が提供されることが一般的です。
保護者の負担軽減
朝の忙しい時間にお弁当を作る必要がないため、保護者は子どもの登園準備に集中できます。また、保育園給食では旬のものを使うことや栄養バランスが考慮されるため、家庭の食事で栄養バランスを気にしすぎなくてもよくなり、家庭の献立へのプレッシャーが軽減されるという利点があります。
食育の推進
保育園では食に専門的な栄養士や調理師が関与しているため、家庭だけで担うより安心感があります。“好き嫌いの克服”や“食事マナー”など、食事の時間を通して子どもに食の大切さを伝えることも保育園と分担できることが、精神的な負担軽減にもつながります。
一方で、給食を提供するにはいくつかの課題もあります。
給食提供で直面する課題
人材確保の難しさ
栄養士・調理師の確保が困難になることがあります。給与水準の低さや勤務時間の厳しさが関係しています。人材確保の難しさは、給食の質や安全性に直結する重要な経営課題です。単なる“人手不足”ではなく「専門性の高い人材が長く働ける環境づくり」が求められています。
コストの上昇
食材費・人件費・光熱費が高騰しています。食材費の高騰により、栄養バランスや旬の食材を取り入れた献立の維持が難しくなり、結果として子どもたちの「食べる体験」や「食育の質」が低下するおそれがあります。また、人件費や光熱費といった給食にかかる見えないコストも上昇しています。特に自園調理を行っている園では、影響が大きくなります。
委託・外注のジレンマ
自園調理が理想ではありますが、委託によるコスト削減や人材確保も現実的な選択肢となってきています。給食を自園調理で続けたいが人手が足りない、外部委託すれば人手は解決するが、給食の質が下がるかもしれないといった効率と教育的価値のバランスをどう取るかが鍵となります。
このように保育園給食は、子どもの発育・教育・家庭支援を同時に担う一方で、その持続には人・モノ・お金の継続的な確保と運営の工夫が不可欠であり、現場や経営層にとっての共通課題となっています。
保育園・幼稚園・認定こども園それぞれの給食の違い
保育園と幼稚園の給食には、制度上いくつかの違いがあります。また、認定こども園の給食提供はどのように行われているのでしょうか?
保育園対幼稚園の給食の違い
給食の提供義務
保育園
厚生労働省の管轄で、給食の提供が義務付けられています。特に認可保育園では、園内に調理室を設けて、栄養バランスの取れた食事を提供する必要があります。
幼稚園
文部科学省の管轄で、給食の提供は義務ではありません。園の方針によって毎日給食がある園もあれば、お弁当持参の日がある園もあります。
調理方法と提供形態
保育園
多くは園内調理(自園調理)で、温かい食事やアレルギー対応がしやすいのが特徴です。旬の食材や行事食など、食育に力を入れている園もあります。
幼稚園
給食がある場合でも、外部委託(仕出し弁当や給食センター)による提供も多く、園内に調理室がないことも一般的です。
栄養管理とガイドライン
保育園
厚生労働省の「保育所における食事の提供ガイドライン」に基づき、子どもの発育に必要な栄養量を満たすよう設計されています。
幼稚園
法的なガイドラインはありませんが、多くの園では学校給食法などを参考に、栄養バランスに配慮したメニューを提供しています。
制度が複雑なこども園
それでは、こども園の給食提供はどのようになっているのでしょうか?認定こども園には4つのタイプがあり、運営主体や制度面などにも違いがあり、当然給食提供の義務にも違いがあります。
認定こども園に関しては以下の記事もご参照ください
幼保連携型こども園
幼稚園と保育園の両機能を併せ持つ施設のため、保育園と同様給食の提供が義務づけられており、栄養管理や衛生管理も保育所基準に準拠しています。
幼稚園型こども園
幼稚園が保育機能を追加して認定を受けた施設となるため、給食提供は義務ではなく、実施は園の裁量となっています。義務ではありませんが、実施している園も多いです。
保育所型こども園
保育所が教育機能を追加して認定を受けた施設になるため、保育園と同様給食の提供が義務づけられています。
地域裁量型こども園
認可外施設などが地域の判断で認定を受けた施設になるため、給食提供が自治体の判断で決められています。
このように幼稚園は園に任されていますが、認可保育園では『子供の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない』と児童福祉法で規定されており、栄養管理が行われた食事を提供する事が必要があるという点が異なっています。また、認定こども園の給食提供については、4つの類型があり、給食の提供義務はそれぞれ異なります。幼保連携型と保育所型では保育園と同様に給食の提供が義務であり、自園調理を基本とした栄養・衛生管理が求められます。一方で、幼稚園型は給食提供は義務ではなく園の裁量であり、地域裁量型は自治体の判断により提供の有無が異なっています。
自園調理と外部委託による提供方法の違い
給食の提供には主に2つの方法があります。それぞれに特徴とメリット・デメリットがあるため、園の方針や体制に応じて選択することが必要です。
自園調理(直営方式)
園内に調理室を設け、園が直接スタッフ(調理師・栄養士)を雇用して給食を提供します。献立作成から調理、配膳、片付けまで園内で完結するため、アレルギー対応や食材の変更、量の調整などがしやすく、保護者との信頼関係を築きやすいというメリットがあります。一方で、調理はもちろん、献立作成・食材の発注等の事務作業すべてを担うことになるのでスタッフにかかる負担も多く、人材の確保が難しく、コストがかかるというデメリットもあります。
外部委託(給食委託方式)
給食業務を外部の専門業者に委託します。外部に委託する方法の中でもさらに、園内で調理する「現地調理方式」と、外部施設で調理して搬入する「セントラルキッチン方式」があります。一般的には、保育園は「現地調理方式」幼稚園では「セントラルキッチン方式」が採用されることが多い傾向です。これらは調理員の採用・教育・衛生管理を業者が担うため、人材確保や管理の負担が軽減し、委託費として、コストの見通しが立てやすいというメリットがあります。一方で、アレルギー対応や個別対応に関しては柔軟な対応が難しい場合もあり、園と調理現場の距離があるため、子どもや保育士とのコミュニケーションが取りづらいというデメリットもあります。
どちらを選択すべきか
給食提供方法(自園調理か外部委託か)を選ぶ際は、園の規模・方針・人材体制・保護者ニーズなどを総合的に考慮し、現場にあった無理のない選択をすることが大切です。自園で調理を行う認可保育園等は、全てを外部委託する方式だけでなく、栄養士・調理師の負担を減らすため、献立作成、発注作業等の一部の事務作業を外部へ委託する(部分的な委託)という選択をするのも1つの方法です。調理以外の作業に業務委託を取り入れることで調理師・栄養士は調理に集中することが可能になり、保育の質を高めることにも繋がります。
”おいしい”が園の個性⁉選ばれる理由は給食にあり
保育園を選ぶ時、保育方針や立地が主な決め手になっているかもしれませんが、今、保護者の関心が高まっているものの1つに給食の質や食育の取り組みがあります。調理現場では、子どもたちに「おいしい」と感じて楽しく食べてもらえるように、五感や心をくすぐるたくさんの工夫をしていますが、こうした工夫は単に「食べさせる」ためではなく、食を通じて心や感性を育てることにもつながっています。
五感を刺激する盛りつけ
色鮮やかな野菜を使ったり、季節のモチーフ(例:紫陽花ゼリーやサンタいちご)を取り入れて、見た目からワクワクさせます。
子どもが関わる体験型食育
野菜の栽培や収穫、簡単な調理体験(梅ジュースづくりやお米の炊飯など)を通して、「自分で作ったから食べてみたい!」という気持ちを引き出します。
子どもの「なんで?」を大切にする
「なんでにんじんってオレンジなの?」「お米ってどうやってできるの?」といった疑問に丁寧に答えることで、食への関心を深めます。
自分で選ぶ・盛りつける
自分の食べられる量を自分で盛り付ける体験を通じて、食への主体性やマナーも育てます。
食後の「おいしかった!」を励みに
子どもたちの反応を日々観察し、やりがいにしながら、味付けやメニューを微調整していくのも現場ならではの工夫です。
子どもたちに喜んでもらえる給食を作るため、調理現場では日々たくさんの工夫をしています。苦手なものを食べることができた、保育園で自分で作ったご飯をお友達と食べたらとってもおいしかったなど、そのような体験を通じて、子どもたちはただ栄養を摂るだけでなく、「食べることって楽しい」「みんなと一緒に食べるって嬉しい」という気持ちを育んでいきます。また、コストをかけずに今からでも取り組める「おいしい!の工夫」は、子どもたちの毎日の園生活に彩りを添え、親にとっての安心材料にも繋がっていきます。
まとめ
保育園の給食は、栄養バランスの取れた食事が提供され、食育の面でも多くのメリットを持っています。また、食を通して社会性やコミュニケーションスキルも身につくため、将来的に仕事や社会生活において必要な能力が培われます。給食を提供するということは、調理だけではなく、日々の保育や職員の連携で作られ、給食は子どもの成長と心を育む“もう一つの保育”です。人員確保やコスト面での課題もありますが、何より給食の時間は子どもたちの笑顔があるれる大切な時間となるため、園に合った方法で給食を提供することと、一人ひとりの関わりが毎日の給食の質を支えています。
弊社は保育士・栄養士の業務負担軽減を目指したBPOサービス(事務業務のサポート)を提供しています。
BPOサービスの利用により、保育園のスタッフは本来やるべき業務に、より一層貴重な時間を割く事ができるようになります。ご紹介したように給食はすぐにでも始められる差別化要因の一つになります。コロナ以降一段と出生率が低下している今、他の施設との差別化は必要不可欠です。今回簡単にご紹介した栄養士業務の一部を外部に委託することでコストの削減はもちろん、より高い専門的なサービスの提供も期待できます。
また我々はDX化にも強みを持ち、保育園の単なるシステム化ではない、仕組みづくりをお手伝いします。人材不足はもちろん、業務効率化ができない、年々コスト増に困っているなど、保育園経営にお悩みの方は是非一度、弊社にご相談下さい!