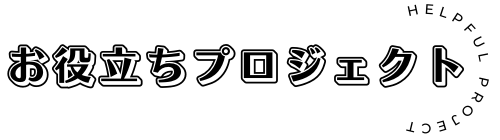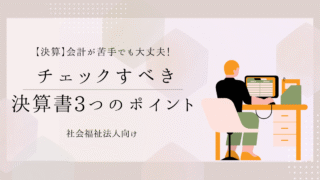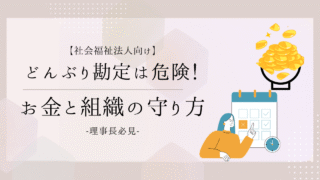問題提起:
社会福祉法人として保育園を運営する理事長にとって、会計は「読む」だけでなく「運用する」ことが重要です。帳票が正しく出ていても、予算・執行・開示・監査がつながっていなければ、現場は改善せず、透明性も担保されません。この記事では、「社会福祉法人会計の基礎」を超えて、現場が回る**運用設計(体制・ルール・チェック)**の作り方を解説します。
記事を読んでわかること:
この記事では、社会福祉法人としての保育園経営における会計の基本を解説します。社会福祉法人会計の特殊な基準や、民営法人との違い、会計処理の具体例など、保育園経営者が知っておくべき重要な以下のポイントを学ぶことができます。
- 民営法人(株式会社)との違いを踏まえた、社福ならではの会計運用の設計原則
- 日次・月次・年次の運用カレンダーと、理事会での見える化フォーマット
- 寄付金・補助金・施設整備の実務管理(目的・財源・使途のひも付け)
- 監査・開示対応を“期末に慌てない”ための準備
- クラウド会計・アウトソーシングを導入するときの失敗しない手順
記事を読むメリット:
この記事を読むことで、社会福祉法人としての保育園経営における会計の基礎を理解し、経営の透明性と信頼性を高めるための具体的な方法を知ることができます。これにより、持続可能な経営を実現し、保護者や地域社会からの信頼を得るための一歩を踏み出せるでしょう。
点検シート(Excel)/決算・監査チェックリスト/投資財源表――記事の内容をそのまま運用に落とせるテンプレ集です。
保育園における会計の重要性と運用設計
会計の重要性
厚生労働省が毎年実施している 「社会福祉施設等調査(厚生労働省)」によると、令和4年10月現在、全国で30,358施設の保育所等があり、うち実に5割強にあたる16,170施設が社会福祉法人によって運営されています。そのため、社会福祉法人が運営する保育園や認定こども園は、子どもたちの成長を支える重要な役割を担っていると言えます。
一方で、保育の質の向上や法改正への対応など、経営を取り巻く環境は日々変化しています。このような状況下で、経営の安定化と持続的な発展のためには、会計情報を正確に把握し、有効に活用することが不可欠です。また会計管理の透明性を確保することで、保護者や地域社会からの信頼を得ることができ、持続可能な運営が可能になります。以下で具体的にどのような場面で会計が関連するか確認してみましょう。
社会的信頼の土台
保育園は公費・保育料・寄附・補助金が混在するため、会計は「数字の記録」ではなく「説明責任の装置」です。正しいプロセスで記録され、理事会・所轄庁・保護者へ説明できる状態が、継続運営の信頼を支えます。
経営判断の速度
月次が遅い=意思決定が遅い、に直結します。試算表の確定日を決め、重要指標(サービス活動増減/事業活動CF/流動比率)だけでも毎月5分で確認できる体制を整えると、配置・採用・投資の判断が早くなります。
人と品質に効く
会計は「保育の質」と無関係に見えますが、資金繰りの安定は職員配置の安定=保育品質の安定につながります。会計を整えることは、現場の安心に直結します。
なぜ「運用設計」が先か
後述しますが、資金収支計算書(C/F)、貸借対照表(B/S)、事業活動計算書(P/L)はそれぞれ
「B/S=体力」「P/L=実力」「C/F=呼吸」
という読み方として重要になります。しかし、読み方が分かっても行動が変わらないと意味がありません。
社会福祉法人会計では、
1)予算(方針)→ 2)執行(証憑・承認)→ 3)月次・四半期レビュー(補正の判断)→ 4)年次決算・監査・開示(説明責任)というひとつながりの運用が前提です。またその法人の性質上、“黒字”より“持続”していること、財務の綺麗さだけでなく、予算に沿って適切に執行され、必要に応じて補正され、最後に説明できることが社会福祉法人の強さになります。この記事は、この「線」を太くするための実務に特化してご説明します。
運用のコツ
①締日・レビュー日をカレンダーに固定
②“P→C→Bの矢印”1枚で理事会へ要点報告
③ズレは「補正」まで想定し、早く直す
社会福祉法人会計とは
民営法人との違い
まず改めての確認となりますが、保育園やこども園を運営する社会福祉法人は、社会福祉法に基づいて設立されており、公益を目的としています。これに対し、民営法人は株式会社や有限会社に代表される、営利活動を目的とした法人になります。以下が具体的な違いです。
設立目的
社会福祉法人は、福祉サービスの提供を目的としており、利益の分配は禁じられています。民営法人は、営利活動を行い、利益を株主に分配することができます。つまり株式会社は株主価値、社会福祉法人は公益の継続を目的とします。成果の物差しが違うため、社会福祉法人では純資産の健全性と事業活動CFの安定を重視します。
監督機関
社会福祉法人は厚生労働省や都道府県の監督下にありますが、民営法人は法務局の監督下にあります。そのため、社会福祉法人では所轄庁・外部監査・情報公開がセットとなります。民営法人は計算書類を持って税務申告することで、最低限の義務を果たせますが、社会福祉法人は計算書類+理事会議事録+注記まで含めて一体で説明する文化が必要です。
財務管理
民営法人は企業会計原則や税法の縛りを反映する決算書の作成が求められますが、社会福祉法人は「社会福祉法人会計基準」に従って会計処理を行い、特定の資金管理や収支計算が求められます。支払資金を軸に「事業/施設整備等/その他」の3区分で運用するのが特徴的です。補助金・寄附は使途の縛りがあり、予算・使途・実績の突合が要となります。`
特殊な会計基準
前述したように、保育園やこども園を運営する社会福祉法人には、一般企業とは異なる「社会福祉法人会計基準」が適用されます。保育園の主な収入源は、保育料、補助金、その他の収入(行事収入など)です。一方、支出は人件費(保育士、調理師など)、運営費(光熱費、消耗品費など)、固定費(賃借料、修繕費など)が中心となります。これらの収支を事業ごとに分けて管理し、各事業の収益性や支出状況を明確にする必要があります。
資金収支計算書、貸借対照表、事業活動計算書の役割
社会福祉法人会計基準に基づき、資金収支計算書と貸借対照表、事業活動計算書を作成する必要があります。
資金収支計算書
保育料収入、補助金、寄付金などの収入と、人件費、運営費、設備費などの支出を記録し、特定の期間内の財務活動を明らかにします。これにより、収支のバランスや資金の使用状況を把握することができます。
貸借対照表
現金、預金、施設設備などの資産と、借入金、未払い金などの負債、および寄付金、積立金などの純資産の状況を示します。これにより、組織の財務の健全性や長期的な資金計画の基盤を評価することができます。
事業活動計算書
一般企業の損益計算書に相当し、一定期間における法人の事業活動から生み出された利益を示す書類です。得られた収入、必要な経費を取りまとめ、法人の事業がどれだけの利益を生み出したのかを計算することができます。これにより、事業の収益性が向上しているか、悪化しているかを把握することができます。
もっと詳細に知りたい方はこちらの記事も参照ください
運用カレンダー:日次・月次・四半期・年次で何をするか
日次・週次(現場の詰まりをなくす)
- 証憑の電子保存(クラウド格納/命名ルールを一本化)
- 支払依頼はワークフローで回す(起票→承認→支払)。小口現金は極力キャッシュレス。
- 寄付・補助の使途は起票段階で目的コードを付与(後で集計が楽になる)。
月次(5分点検+補正判断の下準備)
- 試算表の確定日を決める(例:翌月20日まで)。
- 月次レビューは理事長の5分点検(別記事のチェック表を活用)+未収・未払のエイジング。
- 予算対比で差が中以上なら、担当と原因を1行でメモ(稼働/単価/人員/季節性/一時要因)。
四半期(小さな決算)
- 補助・寄附の執行状況を中間で棚卸し(使途・残高・返還リスク)。
- 設備投資台帳と財源表の突合(補助採択・借入実行・内部留保取り崩し)。
- 労務費の構造(配置・時間外・代替要員)を人事と合同レビュー。
年次(“走りながら締める”ための設計)
- 決算スケジュール表(残高確定→棚卸→減価償却→補助・寄附の注記→監査→理事会承認→開示)。
- 注記は早めに叩き台を作る(補助金・寄附の受入と使途、重要な契約・偶発債務等)。
- 監査資料パッケージ(試算表・補助簿・証憑サンプル・内部規程・理事会議事録)をテンプレ化。
社会福祉法人会計の特徴
寄付金や補助金の扱い
保育園やこども園では、寄付金や補助金が重要な収入源となります。これらの収入は特定の用途に使用されることが多く、適切な管理が求められます。
寄付金
受領した時点で収入として計上されます。用途が指定されている場合、その用途に従って支出を管理し、使用状況を報告する必要があります。
- 目的指定の有無を必ず記録。目的付きは資金の別管理と報告が必要。
- 項目名は後で見返して分かるように(例:寄付_2025地域連携_遊具更新)。
補助金
国や地方自治体からの支援金であり、条件に基づいて収入認識を行います。例えば、運営補助金や設備投資補助金などがあります。
- 採択通知→精算→報告の三点セットで管理。
- 事業費の補助対象・対象外を仕訳段階で分けると、報告時に迷わない。
- 返還リスクがあるものは注記で早めに言及。
固定資産の減価償却
保育園やこども園が保有する建物や設備などの固定資産は、購入時に全てが経費になるのではなく、利用可能な期間などに応じて、使用による価値の減少とし、会計上反映するために減価償却が行われます。減価償却は、以下のように計上されます。
耐用年数の設定
資産の種類に応じて耐用年数を設定し、その期間にわたって資産価値を分割して計上します。
償却方法
定額法や定率法などの方法がありますが、社会福祉法人会計基準に従って適切な方法を選択します。
- 減価償却はリスト化(耐用年数・償却方法・残存簿価)。修繕との線引きもルール化。
事業収益と事業費の考え方
保育園やこども園の事業収益とは、保育料や補助金などの収入です。これには、利用者からの負担金やサービス提供による収入が含まれます。一方、事業費はそのサービス提供に伴う費用を指します。以下のポイントに注意します。
収益の適正管理
収益は事業ごとに区分して管理し、各事業の収益性を評価します。
費用の明確化
事業費は直接費(人件費、材料費)と間接費(管理費、運営費)に分けて計上します。
- 案件台帳に、見積・契約・進捗・検収・支払・財源表(補助/借入/内部留保)を一体管理。
- 借入は返済表を理事会で共有(来期のピーク月を明示)。
“今日から回せる”社福版テンプレ3点セット
P→C→Bの読み方を運用に直結させるための実務フォーマットを用意しました。
社会福祉法人会計の注意点
監査と開示(“慌てない”ための実務)
保育園やこども園を運営する社会福祉法人は、一定規模以上になると外部監査が義務付けられます。監査は、財務諸表の信頼性を確保し、不正や誤謬を防ぐために行われます。
監査の種類
公認会計士や監査法人による外部監査、企業内部の独立した部門が行う内部監査があります。外部監査は第三者の視点で行われるため、透明性が高まります。
財務情報の開示
財務諸表や事業報告書を公開し、保護者や地域社会に対して組織の経営状況を明らかにします。
ポイント!
内部規程(会計規程・経理規程・旅費規程など)を最新版に。改定履歴を残す。
職務分掌:起票・承認・記録・保管の分離。小規模でも「クロスチェック」を仕組みに。
監査前レビュー:
- 未収・未払のエイジングに古い残高がないか
- 補助・寄附の証憑が目的に沿っているか
- 注記の重要性判断(重要な契約、偶発債務、後発事象)
法改正への対応
保育園やこども園に関する法規制は、時折改正されます。これに対応するためには、常に最新の情報を収集し、適切な会計処理を行うことが必要です。
情報収集
法改正に関する情報を収集し、必要な対応を迅速に行います。専門のコンサルタントや会計士の助言を得ることも有効です。
会計処理の変更
法改正に伴う会計基準や開示要件の変更に対応し、財務報告を適正に行います。
社会福祉法人会計の効率化方法
会計ソフトの活用
保育園やこども園を運営する社会福祉法人にとって、会計ソフトの活用は業務の効率化に大きく貢献します。以下の機能を持つ会計ソフトを導入することで、会計処理の精度とスピードが向上します。
自動仕訳機能
日常の取引を自動的に仕訳し、記帳作業を簡素化します。例えば、保育料の入金や支出の自動仕訳により、入力ミスを減らします。
財務諸表の自動作成
収支計算書や貸借対照表を自動的に生成し、定期的な報告が迅速に行えます。
予算管理機能
予算の設定と実績の比較が容易になり、資金管理が効率的に行えます。
クラウド会計のメリット
クラウド会計を導入することで、保育園やこども園の会計業務はさらに効率化されます。クラウド会計の主なメリットは以下の通りです。
リアルタイムデータの共有
複数の担当者が同時に最新の会計データにアクセスできるため、情報の共有がスムーズです。特に、複数の園を運営している場合には大きな利点です。
セキュリティとバックアップ
クラウドサービスは高いセキュリティ基準を満たしており、自動バックアップ機能によりデータの消失リスクを軽減します。
コスト削減
ハードウェアやソフトウェアの導入コストが不要であり、サーバー管理の手間も省けます。
会計業務のアウトソーシング
会計業務を専門の業者にアウトソーシングすることで、内部リソースをより重要な業務に集中させることができます。特に、専門知識を持つ業者に委託することで、正確かつ効率的な会計管理が期待できます。
専門知識の活用
最新の法規制に対応し、専門的な会計処理を行うことができます。これにより、法令遵守が確実に行われます。
業務負担の軽減
定期的な会計処理や監査対応など、煩雑な業務を委託することで、内部の業務負担を軽減します。
コスト効果
アウトソーシングにより、専門スタッフの採用や教育にかかるコストを削減できます。
クラウド会計/アウトソーシング導入の手順(失敗しない進め方)
- 要件定義:園数・利用者数・補助金の種類・ワークフロー(起票~承認)・証憑電子化の範囲。
- トライアル:1園分/1か月分だけ並走記帳して、導入前後の手数とエラー率を比較。
- テンプレ化:勘定科目・部門・補助コード・目的コードを先に固定。後から変えると地獄。
- 権限設計:起票者、承認者、参照のみ等をロールで付与。監査用の閲覧アカウントも事前に。
- 運用開始→30日レビュー:エラーの9割は命名ルールとコード付けに起因。最初の30日で直す。
- アウトソースの切り分け:入力・照合は委託、**方針・判断(補正・投資)**は理事長と内部で。
よくある会計ミスと対策
統制環境整備による対策
保育園やこども園の会計でよく見られるミスには、収入の認識誤りや支出の計上漏れがあります。これらのミスを防ぐためには、内部統制の強化と定期的な内部監査が有効です。
内部統制の強化
業務プロセスを標準化し、チェック体制を整えます。職務分掌を明確にし、複数の担当者による確認を行います。
内部監査の実施
定期的に内部監査を行い、会計処理の適正性を確認します。不正や誤謬の早期発見に努めます。
その他Q&A
-
月次が毎回遅れます。どこから直す?
-
締日・レビュー日を固定し、未提出部門は仮計上→翌月精算をルール化。証憑は電子保存に統一。
-
補助金の返還リスクを早期に見つけるには?
-
起票時に目的コード必須、月次で目的別残高表を確認。対象・対象外を仕訳で分けるのがコツ。
-
監査準備で最低限そろえるものは?
-
内部規程・職務分掌・理事会議事録・案件台帳・注記叩き台。これで9割はスムーズに。
まとめ —— 「運用設計」で会計は“組織の力”になる
保育園やこども園を運営する社会福祉法人にとって、適切な会計管理はその透明性と信頼性を確保するために非常に重要です。正確な財務情報は、保護者や地域社会からの信頼を得るための基盤となり、組織の持続可能な運営を支える重要な要素です。
- 予算→執行→補正→決算→開示を1本の線でつなぐ
- 寄附・補助・投資は最初から目的・財源・使途をひも付け管理
- クラウド×テンプレ×権限で、遅れ・ミス・属人化を削減
- 理事会には直感で判断できる1枚資料を必ず添付
これらを通じて、保育園やこども園を運営する社会福祉法人の会計についての基本的な知識を深めて、必要に応じて、専門家のサポートを受けながら一歩一歩進んでいきましょう。
注目の関連記事