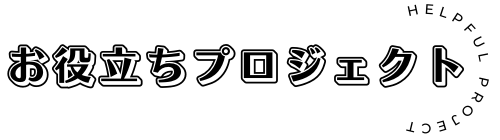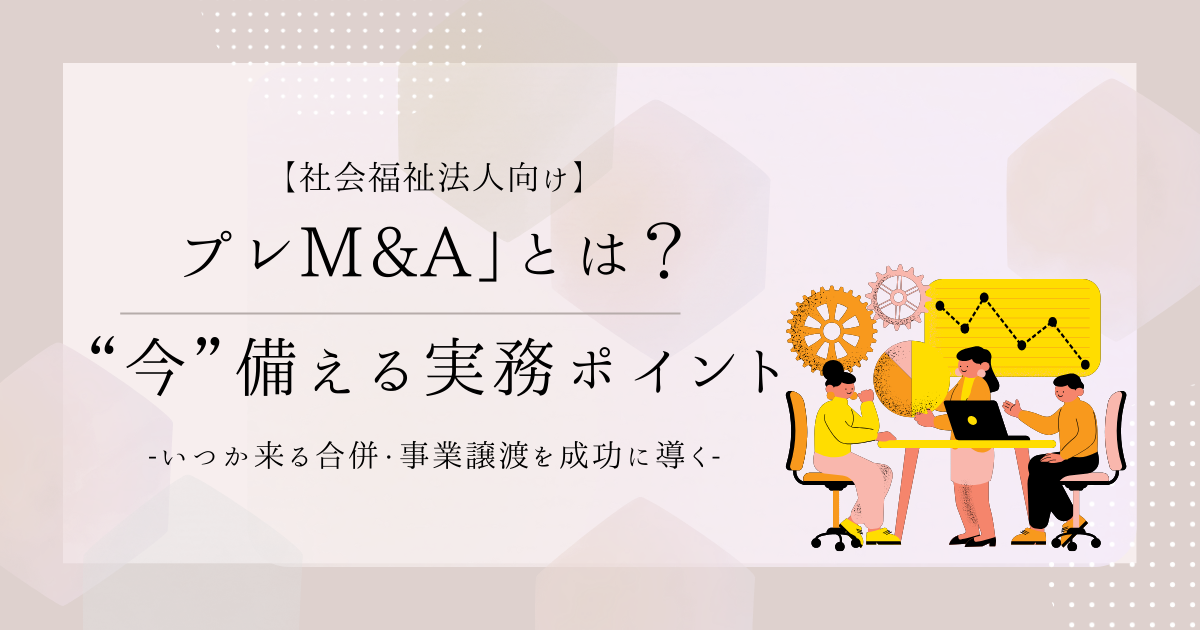いま、理事長が向き合う「プレM&A」
少子化の進行、保育士の採用難、処遇改善の制度変更、物価上昇……保育所運営の外部環境はこの数年で大きく変わりました。これまで「単独での運営」を前提に考えていた社会福祉法人でも、合併や事業譲渡などの再編を“選択肢の一つ”として検討する場面が増えています。
しかし、実行段階に入ってから慌てて整えるのでは遅く、条件交渉で不利になりがちです。鍵になるのが、実行前の**「プレM&A(事前準備)」**。プレM&Aとは、合併・事業譲渡・経営統合などを見据えて、内部の整備・情報の整理・関係者合意の設計を前倒しで進めておく取り組みの総称です。
本記事は、当サイトのハブ記事「脱どんぶり勘定」の実務編として、理事長に向けて**プレM&Aの狙い、制度上の“型”、整備すべき実務、進め方**をやさしく解説します。記事の最後には**準備チェックリスト**を掲載し、**無料のExcel・PPTひな形**のご案内(LP)もご用意しました。まずは全体像を掴み、貴法人の“今”から着手すべき優先順位を明確にしていきましょう。
社会福祉法人のM&Aで押さえる“制度の型”
社会福祉法人の再編は、一般企業のM&Aと比べて**公的枠組み(所轄庁の認可・届出、議決機関の手続)**が密接に関わります。保育所の運営権限や定員等は法律や条例に根拠があるため、手順とタイムラインの設計がとても重要です。まずは「どんな型があるのか」を俯瞰しましょう。
1. 事業譲渡(保育所単位の切り出し)
- 概要:特定の保育所(=事業)を切り出して、別法人へ譲渡。
- ポイント:
- 譲渡対象の価値の見積もり(資産・契約・人材・運営体制など)と、対価の妥当性を示せる資料が必要。
- 債権者保護手続や所轄庁への認可・届出が発生。
- 職員や保護者への説明、引継ぎ計画(シフト・園行事・教材・情報システム等)の事前設計が必須。
2. 合併(吸収合併/新設合併)
- 概要:法人と法人を統合する方法。
- ポイント:
- 所轄庁の認可、理事会・評議員会での決議、財産目録や貸借対照表の整備など、形式的手続が多い。
- 合併後の会計方針、規程体系、人事制度、理事会の運営等を一本化する**PMI(統合)**を前提に、プレ段階で計画しておくことが肝。
3. 認可事項の変更(保育所運営上の必須対応)
- 運営主体、定員、施設長、施設の配置・構造変更などは、児童福祉法・各自治体要綱に基づく認可・届出が必要。
- タイムラインが自治体ごとに異なるため、早期の事前相談で必要書類・審査ポイントを擦り合わせておくのが実務の近道です。
実務Tip
制度の型を最初に決め切る必要はありません。まずは「可能な選択肢」を広げるために、内部の見える化と整備を先行させるのがプレM&Aの考え方です。
プレM&Aのコアは「3つの整備」と「1つの設計」
プレM&Aの本体は、難しいテクニックではなく地に足のついた整備です。特に保育園運営では、**財務・人事労務・園運営(ガバナンス)**を同時並行で整えることが重要。さらに、PMI(統合)から逆算して「どこを揃えるべきか」を先に描いておきます。
1. 財務の整備(脱どんぶり勘定の“実装”)
- 勘定科目・補助科目の再設計:園別/事業別の損益が即時に出る構造へ。共通費配賦のルール(人件費・本部費・減価償却など)も明文化。
- 3年分の月次トレンド整備:売上(保育料・給食費・補助金・加算)、人件費、修繕・設備投資、給食原価、外注費などを園別に比較可能に。
- 仮払・未払の滞留解消:証憑と台帳の紐付けルールを統一。固定資産台帳との整合を取り、**“説明できる残高”**に。
- 補助金・加算の根拠管理:算定根拠・配分ルール・支給実績を台帳化。査定やDD(相手方調査)での即提示が可能に。
狙い:相手方・所轄庁・監査人の誰が見ても「納得感がある」「すぐ再現できる」状態にしておくこと。データの取り出しやすさが交渉のスピードと条件を大きく左右します。
参考:園別P/Lの考え方はハブ記事「脱どんぶり勘定」に詳説。
2. 人事・労務の整備(人件費と加算を“語れる化”)
- 就業規則・給与テーブル・等級制度:職種定義、評価連動、昇降給ルールの文書化。
- 処遇改善等加算の適正管理:算定→配分→支給→エビデンス保管まで、一連の管理プロセスを台帳で可視化。
- 配置基準の遵守状況:年齢別定員・シフト・欠員補充・時間外労働の可視化。
- 社会保険・年休管理:付与ルールの徹底、未消化の扱い、就業実態との整合性チェック。
狙い:人件費は最重要のコストであり、同時に加算の原資です。**“なぜその人件費構造なのか”**を説明できると、候補先との文化・制度の擦り合わせが早まります。
3. 園運営・ガバナンスの整備(安全・記録・意思決定)
- 事故・ヒヤリハット:発生→再発防止策→効果検証までを一つの様式で管理。
- 個人情報・ICT:写真・帳票・連絡帳アプリ・データ持出の権限設計。退職者・委託先・端末管理も含めて統一ルール化。
- 会議体運営:理事会・評議員会の議案書式、稟議ルート、権限委譲基準の可視化。
- 所轄庁・自治体への報告:提出物の年間カレンダー(誰が・いつ・何を)を整備。期日遅延ゼロを目指す。
4. PMI(統合)から逆算した設計
統合後に起きやすい混乱は、評価制度・手当・就業ルール、会計方針、情報システム、園の保育観などの差異です。
プレ段階で「守る/変える」を一度棚卸しし、ロードマップ(1か月以内・3か月・6か月)に落とすと、現場の不安が減り離職を防げます。
小さな実践例
- 「勤怠と給与計算は当面現行維持、評価制度は次年度から新制度に一本化」
- 「写真・個人情報の取り扱いは統合日に全園同一ルールへ」
- 「会計勘定は合併決算期から統一」
こうした統合ポリシーを早い段階で明文化し、労使・保護者・所轄庁それぞれへ同じ説明ができるようにしておきます。
はじめての理事長向け:プレM&Aの7ステップ(実務解説付き)
- ステップ1:目的を言語化する
- ・存続・承継・拡大・人材確保・地域貢献など、優先順位を明確に。
・「何を守り、どこを変えるか」を一文で言えるまで磨く。これが理事会・評議員会、保護者、所轄庁への共通メッセージになります。
- ステップ2:内部整備の計画を立てる
- ・本記事「3つの整備+1つの設計」をToDo化し、担当・期限・様式を決める。
・「まず3園だけ試す」「1か月に1領域だけ進める」など小さく始めて標準化すると、現場の負荷が抑えられます。
- ステップ3:所轄庁に事前相談する
- ・型の妥当性(事業譲渡 or 合併)、必要認可、審査の視点、行政のスケジュール感を早めにすり合わせ。
・行政は「いきなり決定事項の通知」より、「早期相談での段取り共有」を好みます。論点メモを作って持参。
- ステップ4:アドバイザーを選定する
- ・社会福祉法人実務と自治体要綱の両面に強い伴走者が近道。
・役割分担(戦略・財務・人事・法務・PMI)を明確にし、窓口を一本化。外部と内部の連携を“見える化”します。
- ステップ5:相手候補のロングリストを作る
- ・地勢・園児数推移・人材・園の保育観・文化の相性を定性+定量で整理。
・「NG条件(譲れない価値観)」も最初に明確化しておくと、交渉の遠回りを防げます。
- ステップ6:初期情報パッケージを整える
- ・3年分の園別P/L、在籍職員一覧、契約台帳、主要規程一覧、事故・ヒヤリハット記録のサマリー等。
・**“相手に渡せるファイル構成”**で事前に整えると、DDのストレスが激減します。
- ステップ7:理事会・評議員会の合意形成を設計する
- 決議スケジュール、説明スライド、想定Q&A、反対意見への丁寧な回答まで事前に準備。
外向け(保護者・職員・所轄庁)にも伝達計画を用意し、同時多発の不安を抑えます。
事例的な“つまずき”と回避策(よくある3パターン)
パターンA:園別の損益が出せない
- 原因:勘定科目の設計が粗い、共通費の配賦ルールがない、会計ソフトの出力が園横断。
- 回避:勘定・補助の再設計、配賦ルール表の作成、「毎月こう出す」運用手順まで標準化。
- 効果:交渉の初期段階で**“数字で語れる”**。候補先や所轄庁からの信頼が早期に得られます。
パターンB:人事が属人化していて説明できない
- 原因:評価基準・スキル定義が曖昧、加算配分が口約束、勤怠→給与の連携が手作業。
- 回避:就業規則・給与テーブル・評価票の統一、処遇改善等加算の台帳管理、勤怠~給与の突合プロセス整備。
- 効果:統合後の給与・等級制度の摩擦が軽減。退職リスクを抑えられます。
パターンC:所轄庁との段取りが後手に回る
- 原因:「決めてから知らせる」コミュニケーション。必要書類の抜け・審査ポイントの読み違い。
- 回避:早期相談で論点メモを共有。自治体の審査カレンダーを前提に、理事会決議や対外説明のタイミングを逆算。
- 効果:待ち時間のロスが減り、結果として関係者の心理的負担も減ります。
いますぐ使える:プレM&A準備チェックリスト(抜粋)
- 園別・事業別の損益が月次3年分で即時出力できる
- 仮払・未払の滞留がなく、証憑・台帳と突合できる
- 契約台帳(賃貸・リース・委託・保守・SaaS)が最新化されている
- 人件費配賦と加算の根拠(算定→配分→支給)が台帳で説明できる
- 事故・ヒヤリハットの再発防止プロセスが運用され記録されている
- 理事会・評議員会の決裁プロセス・権限が明文化されている
- 所轄庁の事前相談に向けた説明資料(論点・タイムライン・様式一覧)がある
【無料】プレM&A準備セット(Excel+理事会説明PPT)
3年分の園別損益テンプレ、契約台帳、PMIリスク洗い出し表をひとまとめに。
ダウンロード後、そのまま自法人用に調整できます。
FAQ(理事長からよくある質問)
-
そもそも社会福祉法人でも“M&A”は可能ですか?
-
可能です。実務では事業譲渡や合併が中心で、所轄庁の認可・債権者保護・議決機関での決議などの公的手続が求められます。自治体の運用や様式が異なるため、早期の事前相談がスムーズです。
-
事業譲渡の対価はどう考えればよいですか?
-
譲渡対象の価値(資産・契約・収益性・人材など)を合理的に見積もり、対価の妥当性を説明できることが重要です。価値未満の受取は、法人外への資金流出とみなされるリスクがあるため、外部の専門家と算定ロジックを整えておくと安心です。
-
まず何から着手すべきですか?
-
①園別損益の即時出力、②契約台帳の整備、③所轄庁への事前相談準備の3点から始めるのが最短です。この3点が揃うと、候補先との初期対話やDD対応の負荷が一気に下がります。
まとめ:プレM&Aは“準備の質”で8割決まる
プレM&Aは、特別なテクニックではなく、地道な整備の積み重ねです。
- 財務(園別P/L・配賦・台帳・証憑)
- 人事労務(評価・加算・勤怠~給与の整合)
- 園運営・ガバナンス(安全・個人情報・会議体・行政報告)
を先に整え、PMIから逆算した“守る/変える”の設計を行えば、交渉も実行も驚くほどスムーズになります。まずはチェックリストで**「今、どこから着手するか」**を決め、1か月単位の小さな完了を積み上げていきましょう。
無料DL:プレM&A準備セット(Excel+PPT)
本記事のチェックリスト完全版、理事会説明PPT、PMIリスク洗い出し表をまとめてご提供。
▶︎ 無料のテンプレート(Excel・PPT)と伴走支援の詳細はこちら